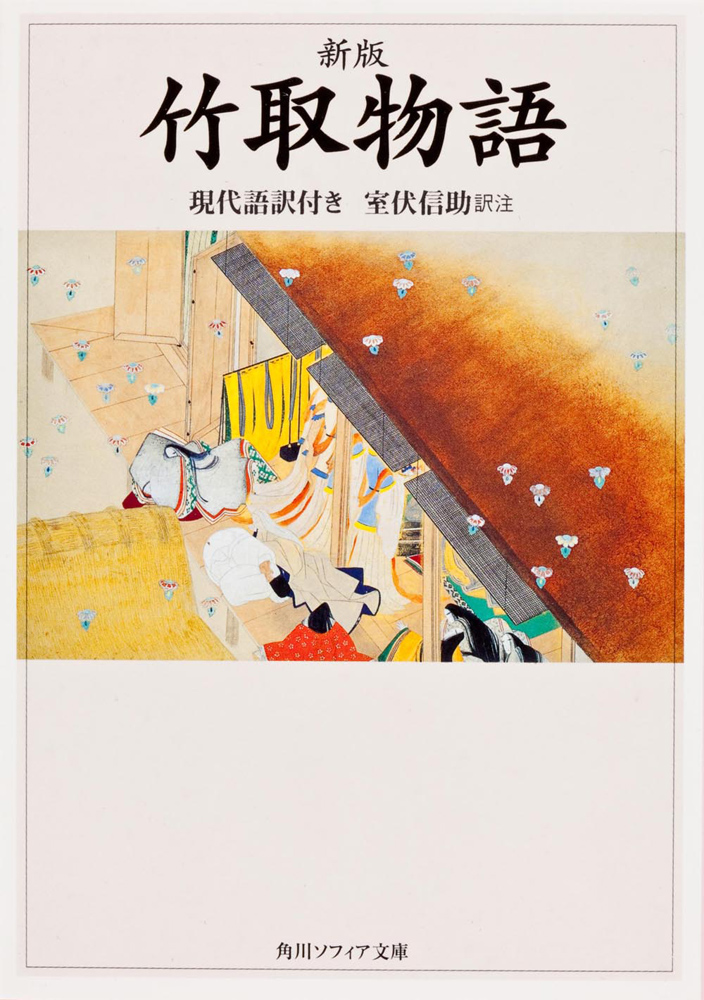藪の中
[
Book Profile
Work
筆者: 芥川龍之介 (1892-1927年、東京生まれ)
発行日: 大正11年(1922年)
ページ数: 20ページ
言語: 日本語
Genre
短編小説・推理小説(不完全)
Time and Place
関山から山科あたり – 旅法師が通った場所
関山とは現在の逢坂山。京都府と滋賀県の境にあり、古来東国から京への入り口として関所がおかれていた。
服装・武器の種類が大正もの。
服装
水干 – 狩衣の一種。民間の常用服。
牟子(女が着ていた) - 市女笠の周囲に、外のすかして見えるような薄物を垂らしたもの。
武器
征矢 - 戦陣に用いる矢。
太刀
どちらも銃などではない。今とはかなり遠い時代。
Subject Matter (内容)
登場人物:
- 木樵り
死体の発見者。
- 旅法師
死んだ男と一緒にいた女の目撃者。
- 放免
多襄丸をからめとった(捕まえた)、検非違使の下役人。
- 媼(おうな)
娘を探している。死んでいた男は自分の婿(娘の旦那)― 死んだ男の義理の母。
- 多襄丸(たじょうまる)
男を殺したと白状している。しかし、女は殺していなく、彼女の行方は知らないらしい。紺の水干を着ている。
- 娘(清水寺に来れる女)
死んだ男の妻。夫を、小刀で殺した、と言っている。
- 死んだ男(巫女の口を借りたる死霊)
殺された男。妻の心を盗人に奪われた。妻の「あの人を殺してください。」という言葉に強い憎しみを持つ。逃げた妻を盗人が追っかけていき、一人きりになった後、落ちていた小刀で自分を刺したと言う。
あらすじ:
山陰の藪の中に死んでいる男をめぐって、死体発見者、生前の被害者の目撃者、放免、殺された男の妻、妻の母、容疑者と名乗る多襄丸、死んだ男の霊の意見を・言い分など、検非違使の質問によって分かった事がそれぞれの立場から書かれている。
注目すべき点:
質問をした検非違使の意見・言い分は一度も作品の中に書かれていない。
結局、だれが男を殺したのかはわからない。誰が嘘の証言をしているのか、それとも全て事実だと言えるのか、最後まではっきりせずに終わっている。
表現方法、本の特徴
一人ずつの証言が、それぞれ分かれた章に書かれている。ナレーションがない。
Essay: それぞれの証言から人間の世間体を守る本性が現れているのではないか
芥川龍之介作「藪の中」では、男が死んだ事件をめぐって、様々な登場人物が自身が体験した、または見たことを元に一人ずつ証言をしていく。しかし、それぞれの証言を照らし合わせてると、事件の真相に食い違いが出てくる。そこで、誰がどのように違うか、その違いによって本人の世間体へどのように影響があるかを考えようと思う。
この事件には主に、多襄丸、死んだ男、その妻の三人が登場する。多襄丸は名高い盗人であり、女好きということで有名であった。また、以前女を殺したことがあるという経歴もある。死んだ男は、若狭の国府の侍であり、名は金沢の武弘と申す。彼の義母によると、優しい気立てで、遺恨など受けるはずはないそうだ。男の妻は名を真砂と申し、まだ十九歳である。母によると、男に劣らぬくらい勝気だという。他にも、検非違使、木樵や旅法師などの人物も登場する。
多襄丸が言うには、女を自分のものにしようとし、男を藪の中でくくりつけ、そこへ妻を呼んだ。そのまま、多襄丸に奪われた。そして、男は殺したが、女には逃げられたというのである。
しかし、女は自分が夫を殺したのだと証言した。女は夫の目の前で多襄丸のものにされ、二人の男に恥じをさらした後に生きていくのは辛いということで、夫に心中を持ちかけた。しかし、夫を刀で刺した後、自分は気を失い、起きたときには夫は死んでおり、自分を殺す勇気がなかったという。
死んだ男本人が、巫女の声を借りて言うには、自分で自身を殺したという。妻を多襄丸に奪われ、今までに見たこともないほど美しい顔で多襄丸を見つめている妻を見て、妻が逃げていき、多襄丸が縄を解いた後、自分を刀で刺し、殺したという言うのだ。
三人とも、自分が殺した証言しており、結局誰が殺したのかはわからないというのがこの作品の結末である。しかし、多襄丸は自分が男を殺したということで、盗人という身分から、位の高い侍を殺したことになり、素晴らしい快挙であり、自慢ができる。女が、自分の恥を見ていた夫をただ殺そうとしたのではなく、共に心中を図ろうとしたことから、まだ夫への愛があったことが説明できる。男は、欲に目がくらんだ上に、盗人に妻を奪われた挙句、盗人または自身の妻に殺されたとすると見栄がなくなってしまい、死後に周りから笑われてしまうかもしてない、または彼の世間体が奪われてしまうかもしれない。しかし、自殺したことにすることにより、潔さが目立つだけではなく、被害者意識が増し、かわいそうだと思ってもらえる。男は、今まで一番美しい顔をした妻を見たと大げさに表現することで、より同感を求めているようにも思える。
これらのことから、証言には自分の世間体を守ろうとする人間の本性が表されているといえるだろう。
Essay: 『羅生門』『藪の中』 映画との比較
『羅生門』という映画では、芥川龍之介の『羅生門』と『藪の中』の話が同時進行で語られている。また、映画の最後に、原作の『藪の中』にはなかった証言を元にしたフラッシュバックが挿入されている。
映画の監督が、二つの作品を一つの作品にまとめたのには、どちらの作品も、人間は自分を守るためならなんでもする、という観点において一致しているからだと考える。『羅生門』の作品では、人間は生きていくためには、どのような罪だろうが犯してしまうという本性が下人によって表されていた。また、人間の心はすぐに変わりやすく、怖いという主題も、映画中の下人に何度も繰り返し語られていた。『藪の中』では、事件についての一人ひとりの証言が異なり、どれも自分の見栄を守るために、自分にとって都合の良いように変わっていることから、人は自分のためなら、他人に嘘をつくこともためらわない、ということが表されている。これらの二つの作品をまとめることで、より人間の本性についての様々なアイデアをつなげることができる。
最後の証言に基づくフラッシュバックは、映画監督自身が考えた、本当は何が起こったのだろうかという真相が描かれている。このフラッシュバックでは、多襄丸、男、女の三人全員にとって、立場の悪い、または見栄の悪い結果となっていた。この挿入により、なぜ三人が違う証言をしなくてはいけなかったのか、嘘をつくことによりそれぞれの見栄がどう守られるかが、原作では疑問だったのに対し、映画でははっきりと示されていた。監督自身の考えた事件内容を加えることにより、『藪の中』の作品の捉え方は様々でかまわないということも分かる。
また、作品の映像化の自由に伴い、複数の小さな変化が加えられている。例えば、木樵が藪の中を歩くシーンを長くすることにより、人目につかないところで事件があったこと、女がさげすむ目を向ける夫に対して、何度も「やめて」と連呼する場面からはどれだけ冷たい目で夫が見ていたかなどが表されている。さらに、おうなの登場を削ることで必要のない情報を与えず、視聴者の理解の妨げになるものを省かれていることもわかる。映画の音響効果においては、旅法師が事件現場に近づくにつれて、音がだんだんと高くなり、ついに目の当たりにしたときに、耳に響くようなすごい高い音を長い間流すことにより、視聴者に高まる緊張感を与えている。
このように、いらないものを省き、文章で説明されていたものを映像だけで表すことにより、話をさらに理解しやすくする工夫がされていると感じた。また、二作品からの様々な要素をつなぎ合わせることにより、人間の本性についての見解が広い視点で捉えられている。その他には、映画にしかできない音響効果を加えることにより、ストーリーにさらに緊張を与え、視聴者の興味を引き付けるのに役立っていると思う。
羅生門
[
Book Profile
Work
筆者: 芥川龍之介 (1892-1927年、東京生まれ)
発行日: 大正四年十一月(1915年)(『帝国文学』)
ページ数: 11ページ
言語: 日本語
Genre
短編小説
Time and Place
平安時代の京都 – 京都が日本の中心だった時代
- 「暮方の事」
芥川には、「蜜柑」(大正八年)「杜子旬」(大正九年)「神々の微笑」(大正十一年)など日暮れが舞台となる作品が多い。
平安京・大内裏の南正門の朱雀門から羅生門まで、南北に走る平安京の中央大通り。現在、京都の千本通りにあたる。
- 洛中
Subject Matter (内容)
登場人物:
- 下人 - 雇われている人、低い身分
羅生門の下で雨やみを待っていた。寂れた朱雀大路で一人さまよっている。羅生門の楼を上ったところで老婆と会う。
比較的若い男性。「大きなにきび」とある。
「短い髭のの中に、赤く膿を持ったにきびのある頬である。」
刀を持っている
- 老婆
羅生門の楼の上で、自分の鬘を作るため、死人の髪の毛を一本一本抜いていた。最後、来ていた着物を下人に持っていかれる。
「檜皮色(ひわだいろ)の着物を着た、背の低い、痩せた、白髪頭の、猿のような老婆である。」
あらすじ:
仕事を失い途方にくれた下人が羅生門の下・朱雀大路で当てもなく、うろうろ彷徨っていた。羅生門の下には、引き取り手のない死人が棄てられていた。死人、盗人などしかいない、寂れた朱雀大路で今後どのようにして生きていこうか悩んでいた。歩き回っていたところ、羅生門の楼の上へ上ってみた。すると、死人が床にごろごろ無造作に転がっていた。そこに、死人の髪の毛を一本ずつ抜いている老婆を見つけた。下人は、持っていた刀で、何をしていたのか言わないとこれで殺すぞと脅す。すると、老婆は自分の鬘を作るためにしていたと分かる。死人は生きるためにひどい事をしてきた。だから、その死人から髪の毛を抜いたところで、悪い事だとしても、許してくれる、という言い分を老婆から聞いた下人は、老婆の着ていた着物を持ち去り、大路の闇へ消えていった。
注目すべき点:
- 人間の本性
- 人間は生きるためには、たとえそれがひどい罪・裏切りでもしてしまうという、飾り立てられていない、本来の人間らしさが描写されている。
- 老婆の行動に対する、下人の反応
- 憎悪を覚える;なぜ?なぜ怒る必要があるのか
- 「この老婆に対すると云っては、語弊があるかも知れない。」
- 「あらゆる悪に対する反感が、一分毎に強さを増してきた」
- 正義の心に燃えていた
- 「餓死するか盗人になるかと云う問題を、改めて持ち出したら、恐らく下人は、何の未練もなく、餓死を選んだことであろう。」
- 「悪を憎む心は、老母の床に挿した松の木片のように、勢よく燃え上り出していた」
- 考え方が自分勝手
- 憎悪を覚える;なぜ?なぜ怒る必要があるのか
- 下人が最後にとった行動
- 老婆から着物を盗み、逃げ去る
- 「では、己が引剥をしようと恨むまいな。己もそうしなければ、餓死をする体なのだ」
- 「下人はすばやく、老婆の着物を剥ぎとった。」à老婆、裸
- 老婆を最初に見たときは、憎悪で、絶対に盗人になりたくないと思っていたはずが、最後には自分が盗人になってしまった。
- 老婆から着物を盗み、逃げ去る
表現方法、本の特徴
- 難しい言葉、歴史的背景の説明が必要な語句には注解がある。
- 英語(フランス語)の使用。「この平安朝の下人のsentimentalismに影響した。」
- 注解:感傷癖。
- 現代らしさ・言語的知的さを出したかった。
- 印象付け。ずっと難しい漢字を用いた日本語から英語がくると、インパクトが大きい。
- 比喩
- 猿のような老婆
- 象徴
- カラスà不吉
- にきび
- ある特定のときににきびを触るà自信のないときに触る
感想
- 気持ち悪い
- 『死』に関する描写が多い。
- 「引き取り手のない死人を、この門へ持って来て、棄てて行くと云う習慣さえ出来た。」
- (鴉が)「門の上にある死人の肉を、啄(ついば)み来るのである。」
- 「幾つかの屍骸が、無造作に棄ててある」
- 「裸の屍骸と、着物を着た屍骸がある」
- 「屍骸の首に両手をかけると、丁度、猿の親が猿の子の虱をとるように、その長い髪の毛を一本ずつ抜きはじめた。」
- 鶏の脚のような、骨と皮ばかりの腕である
- 『死』に関する描写が多い。
Quotation
「餓死をするじゃて、仕方がなくする事じゃわいの。じゃて、その仕方がない事を、よく知っていたこの女は、大方わしのする事も大目にみてくれるであろ」 - 老婆の言い訳
「旧記の記者の語を借りれば」
Essay: なぜ気持ち悪い描写が多いのか
芥川龍之介の有名作、「羅生門」では、作品全体のイメージが「死」であり、その説明が読者に気持ち悪さを与える描写をしている。不快に思わせる表現として、「門の上にある死人の肉を、啄ばみ来るのである。」、「幾つかの屍骸が、無造作に棄ててある」や「裸の屍骸と、着物を着た屍骸がある」などが挙げられる。なぜ芥川龍之介は作品を気持ち悪いと感じさせるような作品に仕上げたのか。それは、気持ち悪いものを読みたいと思う人の心理を理解することが大事だと思う。その心理は、人々がホラー映画を楽しむのと同じ論理なのだと考える。ホラーは刺激的であり、怖くて、不可能と思われる状態からどうやって助かるのか、どうやって化け物と戦うのかなどが興味を引く点である。この作品では、たくさんの人が死んでいってしまう中で、下人がこの先どのようにして生き延びていくのかが読者を引き寄せる要素だと思う。さらに、より身近に、同じような生活の中で起こる出来ことだと感じさせ、ホラーや気持ち悪さの刺激を増すには、現実味が問われる。そこで、芥川龍之介は話の場所設定をあえて、実際に存在する羅生門、現在で言う京都の千本通りを選んだのだと思う。平安時代の期末、かつて栄えていただろう日本の中心の街が廃れているという設定にし、時代背景と照らし合わせていることからも、現実味を出そうとしていることが分かる。
「死」による気持ち悪さを出すことで、読者の興味を引く以外にも、下人への切迫感を出すことが出来ると思う。死人が棄てられていく羅生門の下で雨宿りとしていたとき、まだ下人には盗人になる決心がつかずにいた。しかし、羅生門の楼を上がり、老婆が死人の髪の毛を抜いているのを見て、餓死することを選んだ。しかし、老婆の死人に対する行動の論理を聞いたあと、盗人になる決心がようやくつき、終いには老婆の着物を剥ぎ取って逃げていってしまった。これらの究極の選択は、死と隣り合わせの極致に立たされたときにされたものであり、切迫感が下人の本性を見出すということで大いに活躍したといえると思う。
竹取物語
Book Profile
Work
筆者: 不詳
発行日: 不詳(遅くとも平安時代初期の10世紀半ばまで)
ページ数:
言語: 日本語
Genre
古文 (日本最古の物語)
Time and place
昔の竹取ができるような山がある田舎のような町が設定となっている。
かぐや姫に言い寄ってきた5人はいずれも壬申の乱の功臣で天皇に仕えた人物であることから、奈良時代初期が物語の舞台だったと考えられている。
Subject matter (内容)
登場人物
- かぐや姫
- 翁(本名: 讃岐の造)
- 嫗 ー かぐや姫を育てた
- 石作の皇子(蓬莱の珠の枝: 東の海に蓬莱という山があるので、その山に銀を根とし、金を茎とし、白い珠を実として立っている木がある。その一枝を折って、持ってきてほしい。)
- 庫持の皇子
- 右大巨阿部御主人(火鼠の皮衣)
- 大納言大伴御行
- 中納言石上麻呂足
- 御屋戸斉部の秋田(かぐや姫を「なよ竹のかぐや姫」と名づけた;翁に呼び名をつけるのに呼ばれた)
あらすじ
竹取の翁が、いつものように竹を取っていたところ、光っている竹を見つけ、切ってみたら女の子(かぐや姫と名づけられる)を見つけた。それから、嫗がほんの何年間か育てた。かぐや姫はすごい美人な女性へと育ち、町では美女がいると噂された。それを聞き、実際に彼女を一目見ようと、そして求婚しに、家の前に男の人たちが集まった。かぐや姫が何回も断るにつれ、ほとんどの男性が諦め、去っていった。しかし、五人の貴公子は決して諦めなかった。彼らはかぐや姫と結婚する条件として、それぞれある物を探して来いと命令された。ところが、その命令は不可能に近いものであり、五人の貴公子は全員失敗した。都の帝もかぐや姫がこのうえなく美しいという噂を聞きつけ、かぐや姫に求婚してきたが、貴公子たちに難しい条件を与え、挑戦させたのを無駄にするなど恥ずかしいことはしたくない、と断った。しばらく時が経ち、かぐや姫は翁と嫗に実は人間世界のものではなく、月から来たのだと説明する。そしてまもなく、月の者がかぐや姫を迎えに来、人間世界を去っていった。
注目すべき点
なぜかぐや姫は極めて不可能な条件を五人の貴公子に与えたのか
条件がかなり難しい、または無理だと分かったいた。その上で与えたわけは、月へいつか帰らなくてはいけないと理解していたからだろう。月から来てる身として、人間世界の者と結婚するなど許されない。もし、結婚したとしても、つきに帰る日がそう遠くない将来に待っている。そこで、難しい条件を与えると、それを完璧に解けるものは現れない。つまり月の人間だとばれずに、誰とも結婚しない理由を示すのに最適だったのである。
本の影響、本への社会的影響
女性は顔も知らない男性とでも求婚されたら、結婚し、一門を繁栄するのが社会での役目であり、常識だった。翁はこの時代の一般男性をこの考えを持っていて、
Essay: 主題について
「竹取物語」の作品中では、二種類の愛へのかぐや姫の考えが提示されている。
一つは、「親子愛」である。かぐや姫は翁に見つけられ、オウナに立派な大人へと育ててもらった。その二人に、自分が月の者であると言えずに長い間悩んでいた。その二人を悲しませたくないという思いやりから、かぐや姫には親への愛があるということが分かる。
しかし、親子愛には肯定的だったのに対し、もう一つの「男女愛」へは否定的な考えを持っていると思われる描写がされている。翁は男と女は結ばれ、一門を繁栄すべきだという、当時の時代の特有な考えを持っている。そのため、積極的に求婚を続ける五人の貴公子から一人選び、結婚することをかぐや姫に勧めた。だが、月の者という秘密の理由のため、断る理由を毎回見つけては、拒み続けた。
なぜ月の者は絶対に地球の者とは結婚できない設定なのか。なぜかぐや姫が月の者として設定され、一貫して結婚に否定的な態度を変えない役柄だったのか。それは、筆者自身の思いを作品を通して世に訴えかけるためなのではないかと思う。昔の時代では、身分が高い人は親に決められた、顔を見たこともない人と結婚させられるというのが通常だった。この作品の筆者も、文が書け、作文能力が高い、またこれだけの長い作品を仕上げる時間があったことから、位の高い出で立ちだと思われる。かぐや姫の台詞にもあるように、「顔を見たことがないのに、どうして隙といえましょう。」という疑問、もはやそのような世の中のシステムへの不満がはっきりと描写されている。
これらのことから、「竹取物語」の筆者は自身が抱えている世の中への不満を作品中のかぐや姫を通して主張したかったのだと考える。
Essay: 映画との比較
原作のかぐや姫では、「一.かぐや姫の生い立ち」という章で始まるが、わずか2ページで次の章の「二.貴公子たちの求婚」へ進んでしまう。そして、どのように成長したのかという説明には「三ヶ月ぐらいになるころに、一人前の大きさの人になってしまった」という一文しかない。つまり、原作の筆者が、かぐや姫の子供の頃の成長には重要視していないことが明らかである。それに比べ、映画では貴公子たちの求婚のシーンと同じぐらいの長さで、幼少期の成長が描写されていて、そこで育まれたかぐや姫の自然との触れ合いや、友達との複雑な人間関係などが含まれている。
映画では、原作と同様、かぐや姫が普通の人間よりも成長が倍以上という不自然な要素が含まれていたものの、成長のシーンを長く描写することで不自然を軽減していたように思えた。また、自然に成長していると描写するのに、幼虫が成虫に育つという動物の成長だったり、花のつぼみが開いたり、木の花が紅葉するというような植物の成長の挿絵がされている。これにより、自然と共にすくすくと元気に育ったという印象を視聴者に与える効果があったと思う。挿絵は、映画でしかできないことであり、原作を映画化することの長所が見出されていると感じた。このように自然さを出すことで、かぐや姫の超人間的能力があまり目出さずに、視聴者がストーリーを身近に感じ、自分の周りの環境と比べやすくしたのだと考える。
また、かぐや姫が幼少期に良く共に遊んでいた友達の一人、捨丸との関係が描写されている。子供のときは、一緒に歌いながら山を探検したり、畑から果物を盗んだりと子供らしいことを楽しんだ。しかし、かぐや姫が都の宮廷で宴の途中に飛び出し、超人間的能力で昔住んでいた田舎に行ってみたときには、もう捨丸はこの村にはいないと伝えられた。この時点で、二人の間にすれ違いがあるということが描写されていると感じ取れる。最後に、かぐや姫が都で移動していたところ、お店から鶏を盗み、逃げている捨丸を、車の中から見つけた。しかし、格差の違いに気づかされ、ショックを受けた。車が捨丸を通り過ぎた後、店主に見つかった彼は気を失うほどまで叩かれているのを見て、かぐや姫はひどく心を痛めている様子だった。もともとは同じ位の者同士、仲良く遊んでいたのが、かぐや姫がお金持ちになったせいで二人の関係が壊されてしまったという描写から、映画の監督はこの時代の格差社会の問題について重要視し、視聴者に訴えかけ、今の時代と比較してもらいたかったのだと思う。
キッチン

Book Profile
Work
筆者: 吉本ばなな (1964年、東京生まれ)
発行日: 1988
ページ数: 56
言語: 日本語
Genre
短編小説
Time and Place
吉本ばななは「キッチン」を1980年後半頃(1988)の東京を舞台に書いた。
Subject Matter (内容)
登場人物:
- 桜井みかげ
主人公。先日祖母を亡くす。田辺雄一の提案で彼の家に居候することになる。
- 田辺雄一
みかげと同じ大学の学生。桜井みかげの祖母が生前よく訪れていた花屋でアルバイトしていた。祖母に気に入られていた。祖母を、唯一の家族を亡くした桜井みかげを気遣い、自分の家に住まないかと勧める。母(元・父) と二人暮らし。
- えり子さん
本名、雄司。妻を癌で亡くしてから、性転換をし、女性となった。ゲイバーを経営して、雄一を一人で育ててきた。
あらすじ:
桜井みかげ(主人公)は小さい頃に両親を亡くし、祖父母の元で育った。祖父はみかげが中学に上がるときに亡くなり、祖母と一緒に暮らしていた。しかし、先日その祖母も亡くしてしまい、家に独りぼっちになってしまった。家賃が高いのと、一人で住むには家が大きすぎるので、葬式が終わってまもなく引っ越しをしなければならなくなった。引っ越しについて悩んでいたところ、祖母と仲の良かった田辺陽一が、一緒に彼の家に住まないかと提案してきた。早く出て行かないといけないと思い、新居を探しつつも、田辺宅での生活がこれからもしばらく続いていくようだ。
注目すべき点:
話の中でみかげがキッチンを愛しているということが重要であると思う。
みかげにとってキッチンとは家の中で一番静かで、涼しく、落ち着け、心地よく眠れる場所である。彼女は自分の家のキッチンをすごく気に入っていた。自分の家を引き払ってから居候させてもらっている田辺宅のキッチンも同じぐらいに好きになった。つまり、彼女にとってキッチンとは、どこの家でも唯一心が休まる場所であり、彼女の居場所なのだ。
今後、みかげがどのように生活していくのか
田辺宅を気に入っている様だから、もしかしたら今後田辺雄一との関係が発展していき、このまま共に暮らす可能性は少なくないと思う。みかげは、口を滑らして言ってしまったこと(「おっと、あんまり大声で歌うと、となりで寝てるおばあちゃんが起きちゃう。」pg.55 - おばあちゃんはもういないが、まだいると思ってしまった) を雄一が気を使い、聞いてないふりをし、話題を変えてくれたとき、彼のことを「王子」と例えた。(「とっさに王子になる」pg.55) 気がない人のことを王子と例えるだろうか。最後のシーンで、みかげは「それともいつかまた同じ台所にたつこともあるのだろうか。」と考えている。将来この台所に立つときは、田辺雄一といい関係なって一緒に暮らすようになってからだろう。もしくは、また居候の可能性も。
もしくは、みかげが少し落ち着いてから着々と新居の準備を始め、一人暮らしをはじめたらもう田辺宅にお邪魔することはなくなるかもしれない。(「ここにだって、いつまでもいられない」pg.60)
みかげと宗太郎の関係
宗太郎はみかげが前に付き合っていた恋人である。彼の熱い性格から、みかげは今は宗太郎といたくないという描写がある。田辺家の妙な明るさ、安らぎを彼女は欲しているのである。
宗太郎の目から返ってきた答えには答えられない(「そしてこの気持ちはこのまま、どこか果てしなく遠いところへと消えてゆくのだ。」)àもしほんの少し未練が残っていたとしても、もう宗太郎とよりを戻す(また付き合う)ことはないだろう。 だが、宗太郎は今でもみかげのことが好きである。
表現方法、本の特徴
特に何も起こらず、クライマックスを含むような「起承転結」の形式で書かれてはないが、「転」にあたる「祖母の死」が作品の一番始めに書かれている。これは、ポストモダン主義であるといえる。また異様な設定のえり子さんの存在もポストモダン主義に含まれると思う。
感情・情景を基調に書いている。
Quotation
「魔がさした」pg.13
「私は、この台所をひと目でとても愛した」 pg.17
キッチンの中身の説明 pg.16-17
寂しさを理解しあっている pg.31
「宗太郎は公園が大好きな人だった。」 pg.34
「平和な明るい彼」pg.34
「彼は将来、植物関係の仕事に就きたいそうだ。」 pg.34
「そしてこの気持ちはこのまま、どこか果てしなく遠いところへと消えてゆくのだ。」 pg.38
「この家の人は買い物が病的に好き」「大きい買い物。主に電化製品ね。」pg.39
「生ジュースを飲んで、お肌をきれいにしようと思って」pg.44
「泣くに泣けない妙にわくわくした気持ち」pg.47
「空のかなたに去ってゆく小さい飛行船」pg.49
「おっと、あんまり大声で歌うと、となりで寝てるおばあちゃんが起きちゃう。」 pg.55
「ここが片づいたら、家に帰る途中、公園で屋台のラーメン食べような。」pg.55
「とっさに王子になる」pg.55
「それともいつかまた同じ台所にたつこともあるのだろうか。」pg.60
「ここにだって、いつまでもいられない」pg.60
Essay
吉本ばなな作「キッチン」には、主に作品名の「キッチン」と「死」の二つの象徴が用いられている。みかげの設定の一つとして、キッチンをものすごく好きであるという特徴がある。この作品は、「私がこの世でいちばん好きな場所は台所だと思う。」、「台所であれば食事を作る場所であれば私はつらくない。」という文から始まり、最初の一ページの大半には好みの台所の特徴の説明が書かれている。このような描写から、一目でみかげはキッチンに異常なほどに強い思いがあることがわかる。彼女がこれほどまでにキッチンを好きな理由は、台所とは食事を作る場所であり、食事とは家族とのつながりを表すものであるからだと思う。また、キッチンは日常的に見られる、または使われるものであるということにも、違和感なく、親近感を持って読者に読まれるため、象徴として選ばれたのだと思う。
もう一つの主な象徴として、「死」が挙げられる。作品の二ページ目には、「私、桜井みかげの両親は、そろって若死にしている。そこで祖父母が私を育ててくれた。中学へ上がる頃、祖父が死んだ。そして祖母と二人でずっとやってきたのだ。先日、なんと祖母が死んでしまった。」とみかげの家族全員がもう亡くなってしまったという説明がある。作品の始めにこの重い話題を出し、祖母の死から成長していくみかげを描写していることから、「死」はキッチンの次にかなり重要な象徴だと考える。死とは、家族を亡くすことであり、家族とのつながりを断ち切ってしまうものである。また、突然やってくるものであることから、もう一つの「キッチン」という象徴からはかけ離れていて、対照的だと感じた。
この二つの象徴のように、間逆の結果を与える、まったく別の象徴を用いり、またみかげが祖母の死からどのように新しい人生をスタートしていったかという描写をすることで、人生には様々なことが待ち受けており、それらを乗り越えることにより、人は成長できる、ということを筆者はテーマとして読者に伝えたかったのだと思う。
なぜ「キッチン」と「死」を言葉で書かずに、象徴として表したのかは、その言葉自体に限定されずに、読者のそれぞれの解釈、または考えによって、別の可能性も考えてもらえるからという理由があると思う。限定された言葉だけで考えてもらうのではなく、象徴として使われたものは何にでも置き換えられ、アイデアそのものが大事なのだと感じてもらうことが筆者の目的なのだと考える。「死」という象徴も、本当の「死」だけに限らず、悲しい意味で人生を大きく変えてしまうのしてとらえることができる。そのものにより、ずっと悲しみに浸ってしまうことは必ずしも起こらない、みかげにとって将来の理想の「キッチン」をもつという希望のように、ささいな思いにより、人はその悲しみから立ち直れ、新しい自分へと歩みだせる、ということを吉本ばななは伝えたかったのかもしれない。